1.はじめに
常夏の島バリに行ってきました。
昔、「南太平洋」というミュージカル映画がありました。朗々と歌われた
「バリ・ハイ」という曲のメロディが今でも記憶の底に残っています。
この映画が撮影されたのはバリ島ではなく、物語もバリ島と特定されていた
わけではないようです。しかし、映画「南太平洋=バリ島」というイメージ
があるのではないでしょうか。
近年、日本から沢山の若者がバリ島へ観光に出かけています。
マリンスポーツなどが主な目的だろうと思います。私はマリンスポーツには
興味がありませんが、若いうちに(!)訪ねてみることにしました。
.jpg) キンタマーニ高原からの眺望
2.祈り
キンタマーニ高原からの眺望
2.祈り
バリ島は祈りの島と言えましょう。
多くの人々がさまざまな場所で祈りを捧げ、日常の生活の中に祈りが溶け込
んでいるようです。
.jpg)
郊外の家には、敷地の北東の
位置に祭壇があります。
神聖な場所のため、家人以外
は入れないように閉められてい
ます。
←農家の祭壇
(奥の三角屋根は隣家)
.jpg)
市街地のあちこちに祭壇があります。
門の中の祭壇前では人々が座って祈りを捧げてい
ます。
観光客は門の中に入れません。
←祭壇を飾っている女性
↓一般道路に面した祭壇
.jpg)
.jpg)
由緒ある神社には沢山の参拝者が訪れ
ていました。
←神社内で祭りを待つ人々
↓熱心に祈りを捧げる人々
.jpg)
.jpg)
心の中に悪い考えが潜んでいる人は、
聖水で拭い去ることができます。
←聖なる水で身体を清める人
↓祭りで盛装して歩く人
.jpg)
インドネシアは代表的なイスラム教の国です。
しかし、バリ島は90%以上がヒンズー教徒だそうです。
毎日、神様に供物が捧げられます。
供物は、植物の葉(?)で編んだ皿に花が載せられています。手作りなので
女性の日課になっているようです。
.jpg)
毎朝新しい供物がそれぞれの家で捧げられます。
空港の中の店の前にも供えられます。島のいたる所
が供物であふれています。
3.踊り
バリ島に伝わる代表的な二つの踊りを見学しました。
ケチャダンスとバロンダンスです。
.jpg)
切立った断崖の上にお寺があり、
そのお寺の近くに踊りの野外会場が
ありました。
日没頃から踊りが始まりました。
←お寺を臨むダンス会場
↓日没を背に始まったダンス
.jpg)
およそ40人の裸の若者が座っています。
その若者たちの間に、王子、妃、魔王などの登場人物が現れ、物語りが進行し
ます。
.jpg)
若者たちは、約1時間の踊りの大半を、
「ケチャケチャ、ケチャケチャ」と唱え続
けます。
←魔王の登場
↓妃を閉じ込めた火の輪
.jpg)
ケチャダンスは、バリ古来の土着宗教である太陽崇拝と、海から魔物が上
がってこないように祈る儀式が発展したものだそうです。
これを演ずるのは、地区の人たちのボランティアだそうです。
バロンダンスはお寺の一角で昼間に演じられていました。
バロンダンスも物語が約1時間進行します。
物語は、良い魂を表わす動物バロンと悪い魂を表わす動物ランダの戦いを
表わすそうです。シヴァの神も登場します。
.jpg) ←門の間から現れる登場人物
↓バロンの登場
←門の間から現れる登場人物
↓バロンの登場
.jpg)
.jpg) ←美女の登場
↓女王(だったか?)の踊り
←美女の登場
↓女王(だったか?)の踊り
.jpg)
バリでは、良い魂と悪い魂がいつも同時に存在すると信じられているそう
です。二つの魂の戦いはどちらの勝利でもないままに終わる、という物語に
私は感銘しました。
4.飾り
島のいたるところで複雑な装飾が見られます。
.jpg)
石造の寺院は、門も建物も複雑な
彫刻が施されています。
←通りに面した寺院
.jpg)
美術館はもちろん、通りでも彫刻を楽しむことができ
ます。
←美術館を飾る彫刻
↓
.jpg) ↓通りに面した塔
↓通りに面した塔
.jpg)
.jpg)
村の中心部にあった物見台にも装飾が施され
ていました。
ホテル前の海岸の入り口は、椰子の葉で飾られ
ていました
←村の物見台
↓満月の海岸
.jpg) 5.民家
5.民家
.jpg)
島内の家並は沖縄に似ているようです。
平屋が多く、屋根は茶色の煉瓦で葺かれ、
周囲は石か煉瓦で囲われています。
←海岸に近い村
↓内陸部の村
.jpg)
古い伝統的な村の民家を見学させていただきました。
家は低い塀で囲まれており、北側の入り口を入ると左手(敷地の北東の位置)
に、上述「2.祈り」の最初に掲げた写真の祭壇が設けられていました。
.jpg)
入った右手には炊事場がありました。
煮炊きは釜土でやっているようです。
←炊事場
↓釜土
.jpg)
.jpg)
庭には鶏が放し飼いされています。
闘鶏用の鳥は竹籠に入れられていました。
←放し飼いの鶏
↓闘鶏を入れた籠
.jpg)
.jpg)
小さな建物が数軒かたまっています。
数家族で共同生活をしている模様でした。
←軒が接している家
↓洗濯物を干している軒先
.jpg)
水道が引かれていますが、生水は飲めないので、煮沸して飲むそうです。
お風呂に入る習慣はないようです。
応対してくれた中年の女性二人は背が低く、ほっそりとしていました。
手仕事をしていた老婆二人も背が低く、ほっそりしていました。
村の雰囲気からみて、訪ねた家は中流クラスと推測されましたが、自給自足
で静かに生活している様子でした。日本では戦後間もない頃か、もっと遡っ
た時代の農村風景が想い起こされました。
6.竹
バリでは竹が豊富にあります。
最初に見かけたのは、二階建ての家の工事に、梁を支える支柱として太い竹
が林立している風景でした。
2年前に訪れた上海では、3−4階建てビルの足場を竹で組んでいましたが、
バリでは高層建築がないので足場作りは必要性がないようです。
.jpg)
瓦の代りに竹を使った家がありました。
割竹の内側を上にしていたので、耐久性
を上げるためには外側を上にする工夫が
必要ではないか、などと気になりました。
←竹葺き屋根の家
↓道端に積んだ竹
.jpg)
.jpg)
こちらの竹は何故か群れて育つようです。
日本の竹林のように竹同士の間隔がなく、一箇所
に沢山まとまっています。
小家族制と大家族制の違いでしょうか。
←根元がまとまっている竹
↓
.jpg)
横笛に使えそうな篠竹も見かけました。
節の間隔は50センチ近くありましたので、五本調子などの長い笛も作れそ
うです。もっとも、日本のように厳しい気候で育った竹でないと深い音が出
ないだろう、などと身びいきなことを考えました。
バリでも竹の笛が使われていますが、縦笛ばかりで横笛はないということ
でした。
7.交通
バリ島内には鉄道がありません。
去年(2006年)、私の住んでいる野洲市を訪れたバリからの使節団の人
たちは、新幹線に乗ることを大変楽しみにしていました。
観光バスは沢山走っていますが、路線バスは見かけませんでした。
自動車に負けぬ位の沢山のバイクが目立ちました。
3人乗り、4人乗り(夫婦と子供二人)のバイクも見かけます。小学生くら
いの子供が母親らしい大人を乗せている姿も見かけました。
それ以上に身体がこわばったのは、アクロバット的なバイクでした。
.jpg)
車と車の僅かな隙間をぬってバイクが
割り込み、追い抜いて行く神風バイク!
です。
事故が多いだろうと思っていたら、や
はり発生現場を見かけました。
←バイクの多い道路
↓自動車は左側通行
.jpg) 8.友好
8.友好
ホテルに着いて二日目の夜、テレビをつけてみました。
チャンネルを移動させていたら、NHKの日本語番組が映りました。日本と
同時放映です。
バリ島はインドネシア国の一部であり、インドネシアは独立運動の頃から
親日的なので、という理由でしょうか。バリ島経済の多くは観光収入に負っ
ていると思われますが、観光客の6割は日本人である、という事実にも支え
られていることでしょう。
.jpg) ←ホテルで見た日本語番組
↓日本製陶器が使われているトイレ
←ホテルで見た日本語番組
↓日本製陶器が使われているトイレ
.jpg)
島の至るところで日本製の製品を見かけます。
空港に着いたとき、まず眼に映ったのは日本製の液晶ディスプレイでした。
電気製品で眼についたのは日本製ばかりでした。
自動車もほとんどが日本製です。車が左側通行というのも歓迎です。
私が見た限りでは、ホテルやレストランのトイレには全て日本製の陶器が使
われていました。
もうひとつ強調したいのは、どこでも喫煙OKというおおらかさです。
9.時間
バリ島へ行ったら撮影してみたい、と想定していた光景がありました。
実は、南半球への旅行は初めてなのです。そこで、屋外に設置されている時
計と建物の日陰の方向を写しておけば、南半球に来た記念になるだろうと考
えたのです。しかし、戸外はおろか、ホテルやレストラン、宿泊室内にも時
計を見つけることはできませんでした。
.jpg)
会社の仕事は夕方4時半には終わるそ
うです。
人々の動作はゆったりとしています。
(神風バイクだけは別格です)
←サーファーたちの夕暮れ
↓クタのレストランから見た夕陽
.jpg)
宿泊したのはバリ風の建物の大きなホテルでした。
レストランの前と宿泊棟の中庭にプールがあったので、中庭のプールサイド
で一日過しました。
しかし、旅行代を稼ぎ出そうと請け負った仕事の書類を見ておかなければ
ならなかったため、フランス語を話す娘が近くに来ても、その豊かな胸元に
まで眼を向ける余裕は、これっぽっちも、ありませんでした。
.jpg) ←ホテル中庭のプール
↓吹き抜けのレストラン
←ホテル中庭のプール
↓吹き抜けのレストラン
.jpg) 10.おわりに
10.おわりに
.jpg)
米は年に3回収穫できるそうです。
水田は平地もあれば棚田もあります。
いずれも植え付けと刈り取りは手作業だそう
です。
←山間部のライステラス
為替は1円=77ルピアでした。
レストランで飲むビールは30,000ルピア(約360円)など、数字の
大きさに驚かされます。民家で50,000ルピアで買った縦笛は、空港内
の店では半値でした。ここでは値段は買い手が決め、金持ちが貧乏な人に施
すのは当たり前、ということを本で読んでいたので納得しました。
今回のパックツアー参加者は私たち二人だけでした。
親しくなった38歳の男性現地人ガイドは、親切に私たち年寄りの面倒をみ
てくれました。働きながら高校を卒業した彼は、日本語学校に通い、現在は
テレビの日本語放送で勉強しているそうです。日本の歌謡曲が大好きだそう
で、上手な歌声を披露してくれました。
(散策:2007年10月24〜28日)
(脱稿:2007年11月08日)
-----------------------------------------------------------------
この記事に
感想・質問などを書く・読む ⇒⇒
掲示板
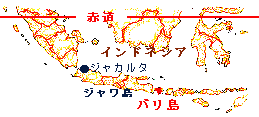
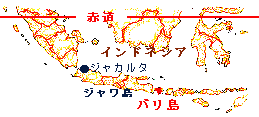
−神々の住む島− バリ島
1.はじめに 常夏の島バリに行ってきました。 昔、「南太平洋」というミュージカル映画がありました。朗々と歌われた 「バリ・ハイ」という曲のメロディが今でも記憶の底に残っています。 この映画が撮影されたのはバリ島ではなく、物語もバリ島と特定されていた わけではないようです。しかし、映画「南太平洋=バリ島」というイメージ があるのではないでしょうか。 近年、日本から沢山の若者がバリ島へ観光に出かけています。 マリンスポーツなどが主な目的だろうと思います。私はマリンスポーツには 興味がありませんが、若いうちに(!)訪ねてみることにしました。キンタマーニ高原からの眺望 2.祈り バリ島は祈りの島と言えましょう。 多くの人々がさまざまな場所で祈りを捧げ、日常の生活の中に祈りが溶け込 んでいるようです。
郊外の家には、敷地の北東の 位置に祭壇があります。 神聖な場所のため、家人以外 は入れないように閉められてい ます。 ←農家の祭壇 (奥の三角屋根は隣家)
市街地のあちこちに祭壇があります。 門の中の祭壇前では人々が座って祈りを捧げてい ます。 観光客は門の中に入れません。 ←祭壇を飾っている女性 ↓一般道路に面した祭壇
.jpg)
由緒ある神社には沢山の参拝者が訪れ ていました。 ←神社内で祭りを待つ人々 ↓熱心に祈りを捧げる人々
.jpg)
心の中に悪い考えが潜んでいる人は、 聖水で拭い去ることができます。 ←聖なる水で身体を清める人 ↓祭りで盛装して歩く人
インドネシアは代表的なイスラム教の国です。 しかし、バリ島は90%以上がヒンズー教徒だそうです。 毎日、神様に供物が捧げられます。 供物は、植物の葉(?)で編んだ皿に花が載せられています。手作りなので 女性の日課になっているようです。
毎朝新しい供物がそれぞれの家で捧げられます。 空港の中の店の前にも供えられます。島のいたる所 が供物であふれています。 3.踊り バリ島に伝わる代表的な二つの踊りを見学しました。 ケチャダンスとバロンダンスです。
切立った断崖の上にお寺があり、 そのお寺の近くに踊りの野外会場が ありました。 日没頃から踊りが始まりました。 ←お寺を臨むダンス会場 ↓日没を背に始まったダンス
およそ40人の裸の若者が座っています。 その若者たちの間に、王子、妃、魔王などの登場人物が現れ、物語りが進行し ます。
若者たちは、約1時間の踊りの大半を、 「ケチャケチャ、ケチャケチャ」と唱え続 けます。 ←魔王の登場 ↓妃を閉じ込めた火の輪
ケチャダンスは、バリ古来の土着宗教である太陽崇拝と、海から魔物が上 がってこないように祈る儀式が発展したものだそうです。 これを演ずるのは、地区の人たちのボランティアだそうです。 バロンダンスはお寺の一角で昼間に演じられていました。 バロンダンスも物語が約1時間進行します。 物語は、良い魂を表わす動物バロンと悪い魂を表わす動物ランダの戦いを 表わすそうです。シヴァの神も登場します。
←門の間から現れる登場人物 ↓バロンの登場
.jpg)
←美女の登場 ↓女王(だったか?)の踊り
バリでは、良い魂と悪い魂がいつも同時に存在すると信じられているそう です。二つの魂の戦いはどちらの勝利でもないままに終わる、という物語に 私は感銘しました。 4.飾り 島のいたるところで複雑な装飾が見られます。
石造の寺院は、門も建物も複雑な 彫刻が施されています。 ←通りに面した寺院
美術館はもちろん、通りでも彫刻を楽しむことができ ます。 ←美術館を飾る彫刻 ↓
↓通りに面した塔
.jpg)
村の中心部にあった物見台にも装飾が施され ていました。 ホテル前の海岸の入り口は、椰子の葉で飾られ ていました ←村の物見台 ↓満月の海岸
5.民家
島内の家並は沖縄に似ているようです。 平屋が多く、屋根は茶色の煉瓦で葺かれ、 周囲は石か煉瓦で囲われています。 ←海岸に近い村 ↓内陸部の村
古い伝統的な村の民家を見学させていただきました。 家は低い塀で囲まれており、北側の入り口を入ると左手(敷地の北東の位置) に、上述「2.祈り」の最初に掲げた写真の祭壇が設けられていました。
入った右手には炊事場がありました。 煮炊きは釜土でやっているようです。 ←炊事場 ↓釜土
.jpg)
庭には鶏が放し飼いされています。 闘鶏用の鳥は竹籠に入れられていました。 ←放し飼いの鶏 ↓闘鶏を入れた籠
.jpg)
小さな建物が数軒かたまっています。 数家族で共同生活をしている模様でした。 ←軒が接している家 ↓洗濯物を干している軒先
水道が引かれていますが、生水は飲めないので、煮沸して飲むそうです。 お風呂に入る習慣はないようです。 応対してくれた中年の女性二人は背が低く、ほっそりとしていました。 手仕事をしていた老婆二人も背が低く、ほっそりしていました。 村の雰囲気からみて、訪ねた家は中流クラスと推測されましたが、自給自足 で静かに生活している様子でした。日本では戦後間もない頃か、もっと遡っ た時代の農村風景が想い起こされました。 6.竹 バリでは竹が豊富にあります。 最初に見かけたのは、二階建ての家の工事に、梁を支える支柱として太い竹 が林立している風景でした。 2年前に訪れた上海では、3−4階建てビルの足場を竹で組んでいましたが、 バリでは高層建築がないので足場作りは必要性がないようです。
瓦の代りに竹を使った家がありました。 割竹の内側を上にしていたので、耐久性 を上げるためには外側を上にする工夫が 必要ではないか、などと気になりました。 ←竹葺き屋根の家 ↓道端に積んだ竹
.jpg)
こちらの竹は何故か群れて育つようです。 日本の竹林のように竹同士の間隔がなく、一箇所 に沢山まとまっています。 小家族制と大家族制の違いでしょうか。 ←根元がまとまっている竹 ↓
横笛に使えそうな篠竹も見かけました。 節の間隔は50センチ近くありましたので、五本調子などの長い笛も作れそ うです。もっとも、日本のように厳しい気候で育った竹でないと深い音が出 ないだろう、などと身びいきなことを考えました。 バリでも竹の笛が使われていますが、縦笛ばかりで横笛はないということ でした。 7.交通 バリ島内には鉄道がありません。 去年(2006年)、私の住んでいる野洲市を訪れたバリからの使節団の人 たちは、新幹線に乗ることを大変楽しみにしていました。 観光バスは沢山走っていますが、路線バスは見かけませんでした。 自動車に負けぬ位の沢山のバイクが目立ちました。 3人乗り、4人乗り(夫婦と子供二人)のバイクも見かけます。小学生くら いの子供が母親らしい大人を乗せている姿も見かけました。 それ以上に身体がこわばったのは、アクロバット的なバイクでした。
車と車の僅かな隙間をぬってバイクが 割り込み、追い抜いて行く神風バイク! です。 事故が多いだろうと思っていたら、や はり発生現場を見かけました。 ←バイクの多い道路 ↓自動車は左側通行
8.友好 ホテルに着いて二日目の夜、テレビをつけてみました。 チャンネルを移動させていたら、NHKの日本語番組が映りました。日本と 同時放映です。 バリ島はインドネシア国の一部であり、インドネシアは独立運動の頃から 親日的なので、という理由でしょうか。バリ島経済の多くは観光収入に負っ ていると思われますが、観光客の6割は日本人である、という事実にも支え られていることでしょう。
←ホテルで見た日本語番組 ↓日本製陶器が使われているトイレ
島の至るところで日本製の製品を見かけます。 空港に着いたとき、まず眼に映ったのは日本製の液晶ディスプレイでした。 電気製品で眼についたのは日本製ばかりでした。 自動車もほとんどが日本製です。車が左側通行というのも歓迎です。 私が見た限りでは、ホテルやレストランのトイレには全て日本製の陶器が使 われていました。 もうひとつ強調したいのは、どこでも喫煙OKというおおらかさです。 9.時間 バリ島へ行ったら撮影してみたい、と想定していた光景がありました。 実は、南半球への旅行は初めてなのです。そこで、屋外に設置されている時 計と建物の日陰の方向を写しておけば、南半球に来た記念になるだろうと考 えたのです。しかし、戸外はおろか、ホテルやレストラン、宿泊室内にも時 計を見つけることはできませんでした。
会社の仕事は夕方4時半には終わるそ うです。 人々の動作はゆったりとしています。 (神風バイクだけは別格です) ←サーファーたちの夕暮れ ↓クタのレストランから見た夕陽
宿泊したのはバリ風の建物の大きなホテルでした。 レストランの前と宿泊棟の中庭にプールがあったので、中庭のプールサイド で一日過しました。 しかし、旅行代を稼ぎ出そうと請け負った仕事の書類を見ておかなければ ならなかったため、フランス語を話す娘が近くに来ても、その豊かな胸元に まで眼を向ける余裕は、これっぽっちも、ありませんでした。
←ホテル中庭のプール ↓吹き抜けのレストラン
10.おわりに
米は年に3回収穫できるそうです。 水田は平地もあれば棚田もあります。 いずれも植え付けと刈り取りは手作業だそう です。 ←山間部のライステラス 為替は1円=77ルピアでした。 レストランで飲むビールは30,000ルピア(約360円)など、数字の 大きさに驚かされます。民家で50,000ルピアで買った縦笛は、空港内 の店では半値でした。ここでは値段は買い手が決め、金持ちが貧乏な人に施 すのは当たり前、ということを本で読んでいたので納得しました。 今回のパックツアー参加者は私たち二人だけでした。 親しくなった38歳の男性現地人ガイドは、親切に私たち年寄りの面倒をみ てくれました。働きながら高校を卒業した彼は、日本語学校に通い、現在は テレビの日本語放送で勉強しているそうです。日本の歌謡曲が大好きだそう で、上手な歌声を披露してくれました。 (散策:2007年10月24〜28日) (脱稿:2007年11月08日) -----------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ